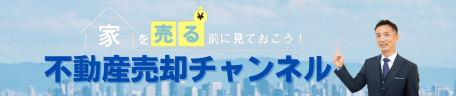コラム
第4回:複数人で相続した不動産を売るには?トラブルを防ぐためのコツと手順
相続した不動産を複数人で共有するケースは少なくありません。
兄弟姉妹、親族など、複数の相続人がひとつの不動産を所有することになると、売却の意思決定や手続きに「全員の合意」が必要になります。
「誰が主導権を持つのか」
「いつ売るのか、いくらで売るのか」
こうしたことを話し合うなかで、感情的な対立やトラブルが生まれることも…。
今回は、共有名義の相続不動産を円滑に売却するための基本的な手順と、トラブルを防ぐためのコツを解説します。
共有名義の不動産を売却するには「全員の同意」が必要
不動産は原則として、共有名義人全員の同意と署名・押印がなければ売却できません。
よくある誤解は「長男が代表して話を進めればOK」というものですが、名義上の共有者が他にいれば、その人の同意がなければ法的に売却は成立しません。
たとえば…
- 遺産分割協議で共有持分を決めた兄弟
- 相続放棄をしていない配偶者や親族
- 登記だけ名義変更していない相続人 など
誰が登記上の所有者になっているのか?をきちんと確認したうえで、関係者全員で話し合いの場を設けることが第一歩です。
よくあるトラブルとその原因
- 意思決定がまとまらない
→「売りたい派」と「売りたくない派」で対立 - 感情的な摩擦
→ 過去の家族関係や介護の不公平感から感情的な対立に発展することも - 情報共有不足
→ 一部の相続人だけが話を進めてしまい、他の人が納得していないケース - 名義が整理されていない
→ 相続登記が済んでおらず、手続きが止まってしまう
これらの問題は、感情だけでなく「手続きへの無理解」や「コミュニケーション不足」から起きることが多いため、冷静に対話と段取りを整えることが大切です。
円満な売却に向けた5つのステップ
① 所有者(共有者)を明確にする
法務局から登記簿謄本を取得して、誰がどの持分を持っているかを確認。
② 全員の意見を聞く場を設ける
感情的な話になる前に、不動産会社など第三者の同席で「情報を共有する場」をつくると円滑です。
③ 遺産分割協議書を作成する
共有名義のまま売却もできますが、可能であれば売却前に1人の名義にまとめると手続きがスムーズ。
④ 相場を提示して方向性を決める
売却する場合、まずは不動産会社に査定を依頼し、相場感を共有することで「金額の感覚差」を埋めることができます。
⑤ 手続きに必要な書類と日程を全員で共有
印鑑証明や委任状、本人確認書類など、事前に準備が必要な書類について周知しておくことで「当日ドタキャン」のリスクを減らせます。
専門家の関与で“冷静な話し合い”が実現しやすくなる
相続した不動産は、家族間だからこそ難しくなることもあります。
そのときに力を発揮するのが、不動産会社や司法書士、税理士など第三者の存在です。
- 感情的な対立が生じそうな場合
- 名義や税金のことで専門知識が必要な場合
- 遺産分割協議が進まない場合
こうしたときは、中立的な立場の専門家を交えることで、関係がこじれずに話が進む可能性が高まります。
Plus4では“家族会議の立ち会い”も行っています
Plus4では、相続不動産の売却に際し、相続人の皆様が集まる場での査定報告・売却説明・質疑応答の立ち会いも行っております。
- 兄弟で意見が食い違っていて困っている
- 代表者が進めているけど他の人が納得していない
- 税金や法律のことも踏まえて冷静に判断したい
こうしたお悩みを持つ方も、ぜひ一度ご相談ください。家族間の“想い”と“現実”のバランスをとりながら、円満な売却をサポートいたします。
まとめ
共有名義の不動産を売却するには、「全員の同意」と「冷静な話し合い」が不可欠です。
話し合いがまとまらないまま時間だけが過ぎてしまうと、不動産の価値が下がってしまったり、固定資産税などの負担が続いてしまうことも。
だからこそ、今このタイミングで“家族での話し合い”をスタートしてみてください。
Plus4が、専門的な視点と丁寧な対応で、家族の“これから”を支えます。